初出;2018/06/05 Vol.279 ねるねるねるねの魔改造
改稿:2022/12/21
ねるねるねるねの魔改造
以前、科学動画で紹介した、魔改造ねるねるねるね。
具体的にナニを入れたのか気になっている方も多いようなので、ここでひとつ、ネタばらしをしていこうと思います。
1.5番の液:ブルーマロウ抽出液
まずは1.5番の液。あからさまに毒々しい色をした液体ですが、その正体はブルーマロウという青い花の抽出液です。
このブルーマロウやバタフライピーなどは青いハーブティーとして知られていますが、アントシアニン系色素でpHで変色するという働きがあります。
通販などで安く買えます。少量の水で湿らせてしばらくしてから絞るとヤバいくらい濃い色素が取れるのは・・・動画を見てもらえばおわかりですね(笑)。
ちなみに酸による変化は、レモン汁などを注いでも良い訳で、それを利用して色の変わる飲み物を、というのも面白いです。実際、この働きのために、青いハーブティーが紫に変化する訳ですね。
色々応用して試してみてはいかがでしょうか。
なお、ブルーマロウやバタフライピーの他には、紫キャベツのあの色もアントシアニンによるものです。
1.7番の粉:重曹
1.7番の粉は「重曹」です。
ねるねるねるねは、グアーガムなどの増粘多糖類(ネバネバ成分)とデンプン質(ベース)と水でねっちりしたものになるところに重曹が入っています。
で、マシマシにするために動画では追い重曹を入れた次第です。
この重曹が、2番の粉に含まれる酸と反応して炭酸ガスが発生し、それが粘性の高い基剤に捕まって発泡状態となります。
また、酸が入ってpHが変化するため、中の着色料が変色を起こし「色が変わって・・・へっへっへ」という仕組みです。
2.5番の粉:クエン酸(動画では酒石酸)
さて、2番の粉のパワーみをアップさせるために、2.5番の粉としてさらに酸を追加します。
クエン酸で十分かとも思ったのですが・・・動画ではより凶悪な酸味を味わってもらうために、さらに酸っぱさマシマシの酒石酸を使いました。
その割にうつ氏のリアクションが薄かったので中和してマズくなっただけかと思った・・・んだけどそうではなかった・・・悶絶ものに酸っぱい!
素晴らしき知育菓子
改めて振り返ると、
重曹+酸で発生した炭酸ガス&ネバネバ基剤でシュワシュワ発泡、さらにpH変化で着色料が変色
という仕組みです。科学的には非常に簡単ですが、少量の水をいれるだけで誰でも簡単にしかも安定的にねっちりした質感を出すというのはまさに職人芸で、知育菓子としての本懐は実はそこだったりします。
お菓子もそういった意味で、どうやってこのお菓子が成り立っているのか・・・を考えると意外な発見があるかもしれません。
ねるねるねるねで遊ぶ動画
ねるねるねるねや他の知育菓子も含めて、色々と遊んでみた動画は他にもあるのでぜひ。
思いっきりIQが下がっているのが特徴(笑)
著者紹介

作家、科学監修。「科学は楽しい!」を広めるため科学書分野で20年以上活動。著作「アリエナイ理科」シリーズ累計50万部突破。原作を務めるコミックス「科学はすべてを解決する!!」も50万部を超える。著作「アリエナクナイ科学ノ教科書」が第49回・星雲賞ノンフィクション部門を受賞。週刊少年ジャンプ連載「Dr.STONE」においては漫画/アニメ共に科学監修を担当。TV番組「世界一受けたい授業」「笑神様は突然に・・・」NHK「沼にハマってきいてみた」等に出演。ゲーム実況者集団「主役は我々だ!」と100万再生を超えるYouTube科学動画を多数共同製作。独自YouTubeチャンネル「科学はすべてを解決する!」チャンネル約30万登録やTwitterフォロワー16万人以上。教育系クリエイターとして注目されている。関連情報は https://twitter.com/reraku
「アリエナイ毒性学事典」好評発売中です!
「アリエナクナイ科学ノ教科書2」好評発売中です!
新刊「マンガでわかる! 今日からドヤれる科学リテラシー講座 教えて!夜子先生」好評発売中です!
宣伝
ニコニコ動画にて有料チャンネル「科学はすべてを解決する!! ニコニコ秘密基地」を開設しました!

「アリエナイ理科式世界征服マニュアル」が改訂版となって新発売されます!
「アリエナイ医学事典2」好評発売中です!
「アリエナイ医学事典 改訂版」好評発売中です!
「アリエナイ理科ノ大事典3」、好評発売中です!
くられ先生の単著「アリエナイ毒性学事典」好評発売中です!
工作系に特化した「アリエナイ工作事典」好評発売中です!
「アリエナイ理科ノ大事典」改訂版が発売中です!
「アリエナイ理科ノ大事典2」、好評発売中です。


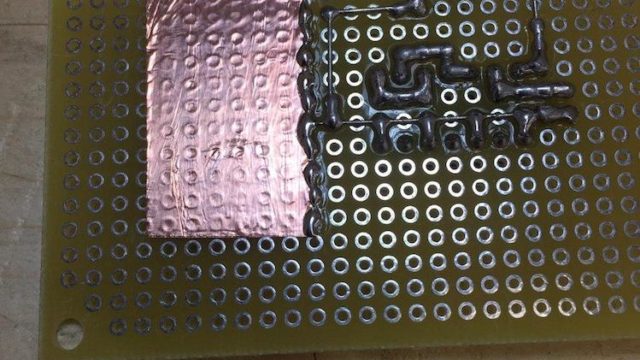


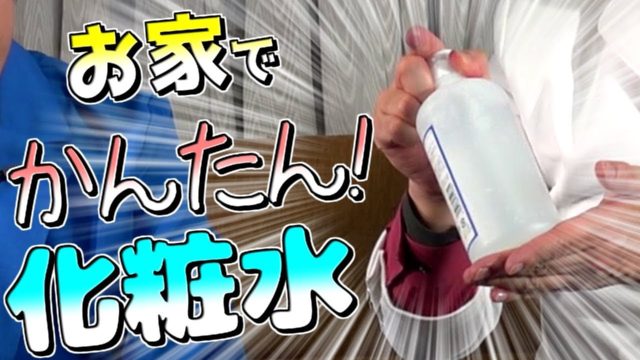
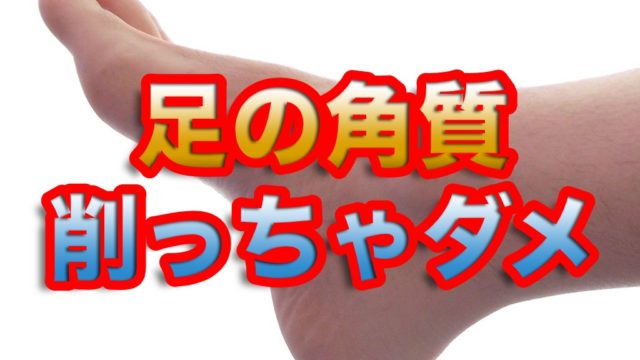
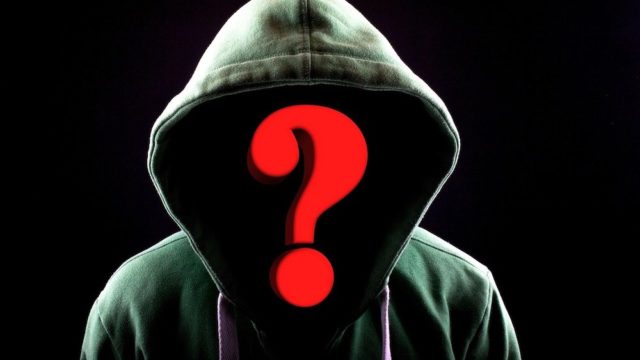
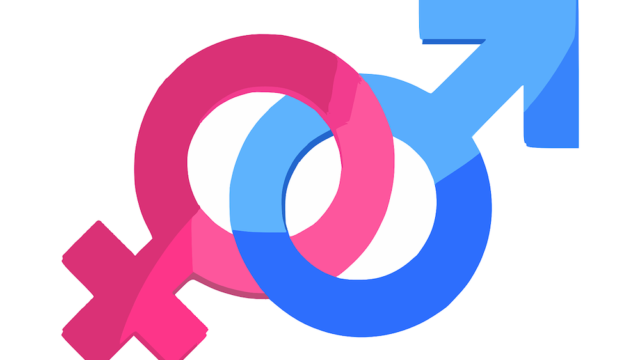

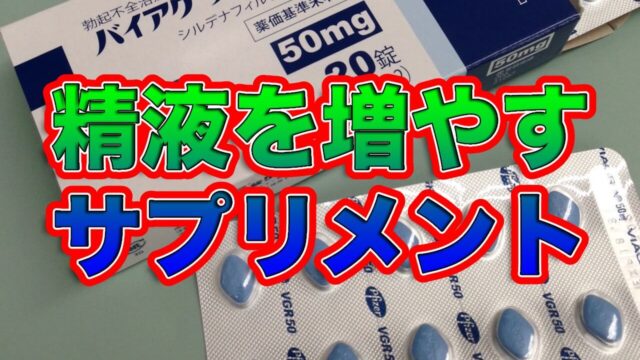
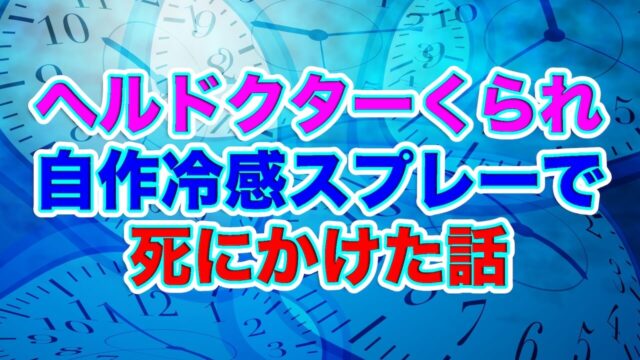




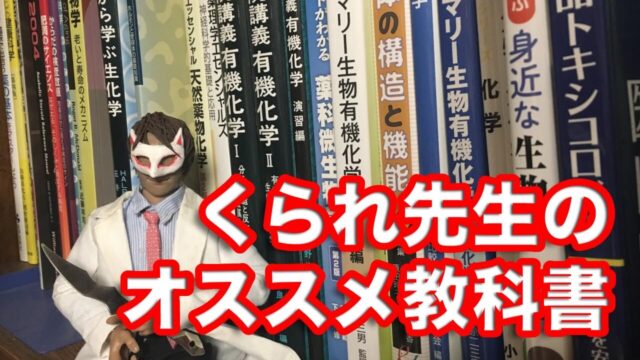
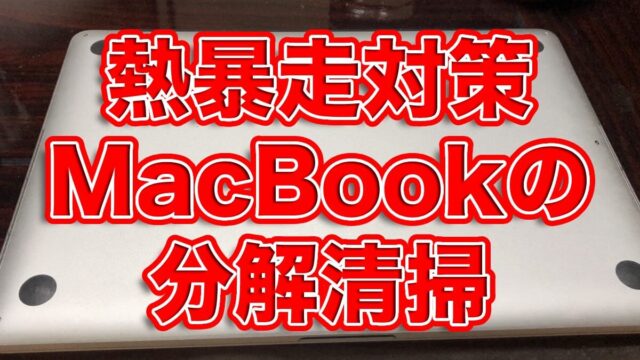

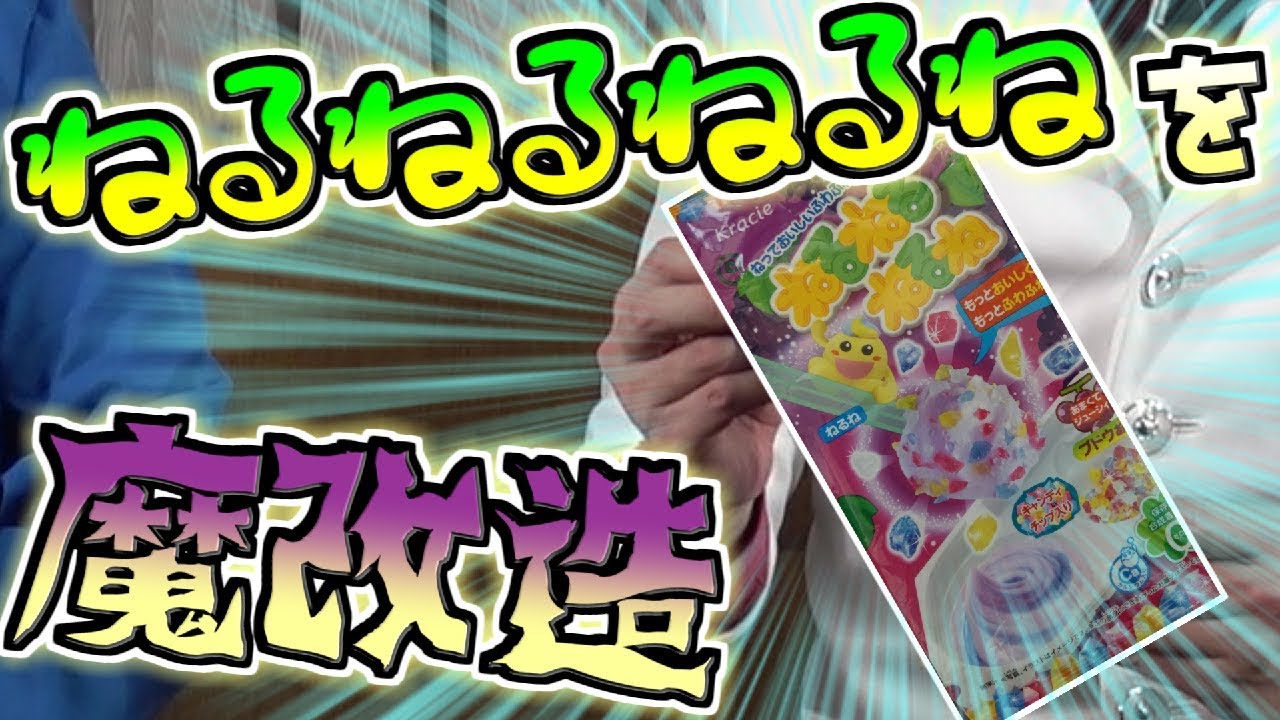
















![NICHIGA(ニチガ) AGC 重曹 1kg 食品添加物 炭酸水素ナトリウム 国産重曹 [01]](https://m.media-amazon.com/images/I/51JrYEO11IS._SL160_.jpg)















![無水クエン酸 950g 食用 純度99.5%以上 [高純度クエン酸]](https://m.media-amazon.com/images/I/51EOAx2rDAL._SL160_.jpg)










































































