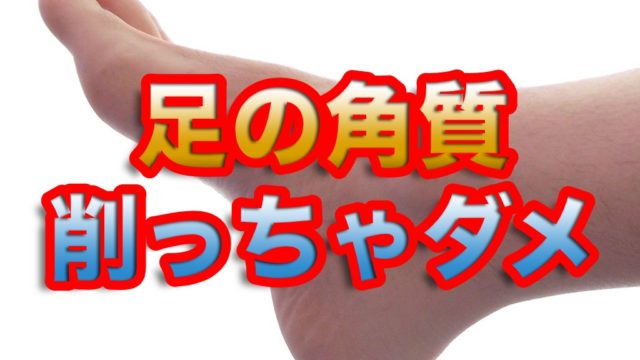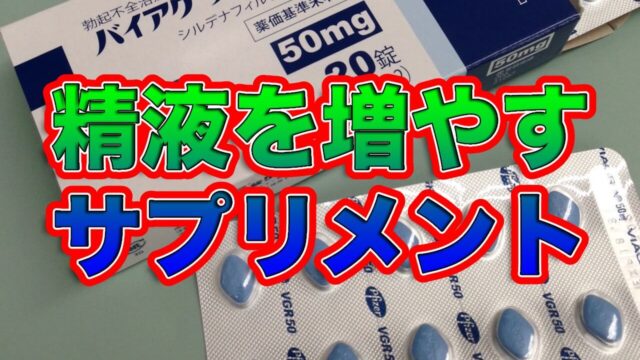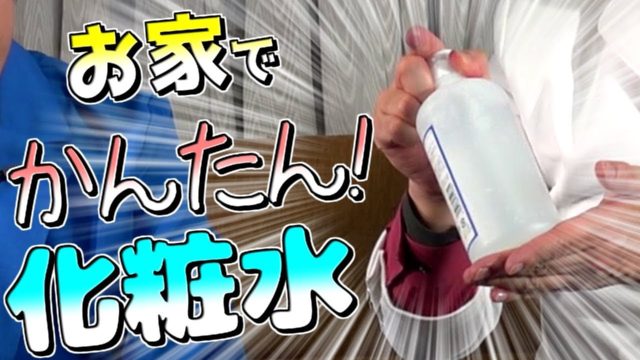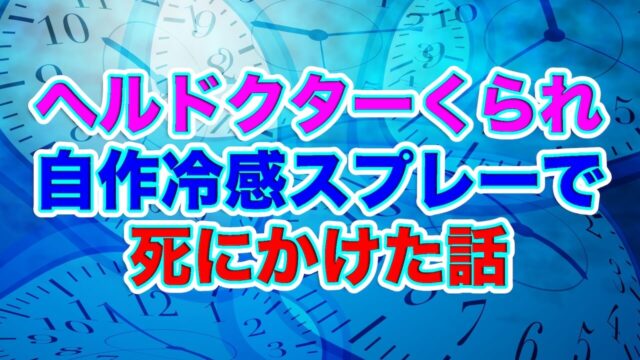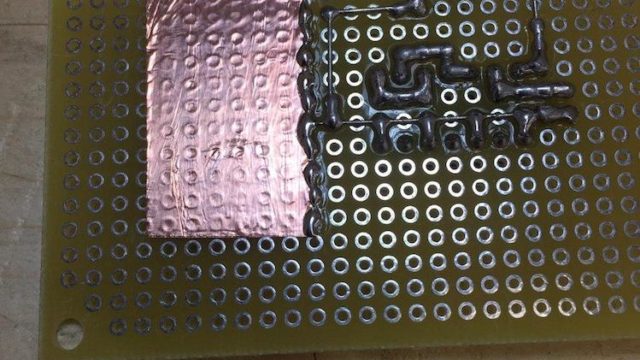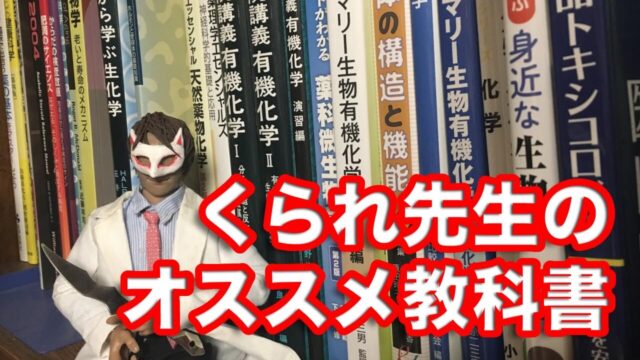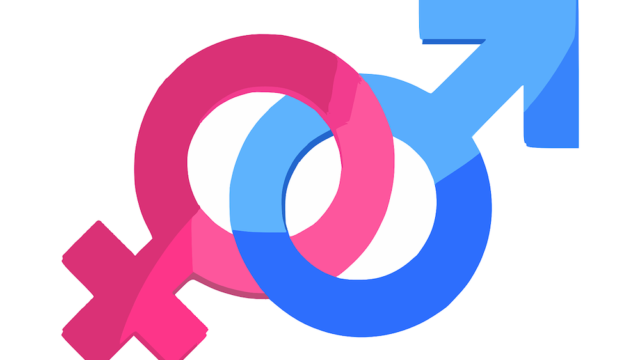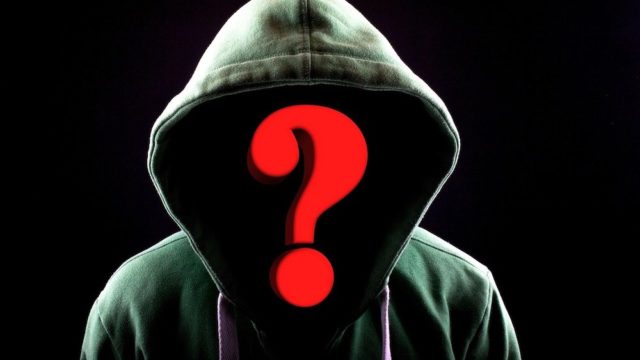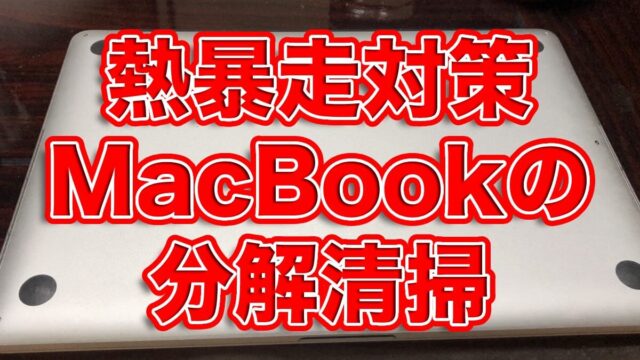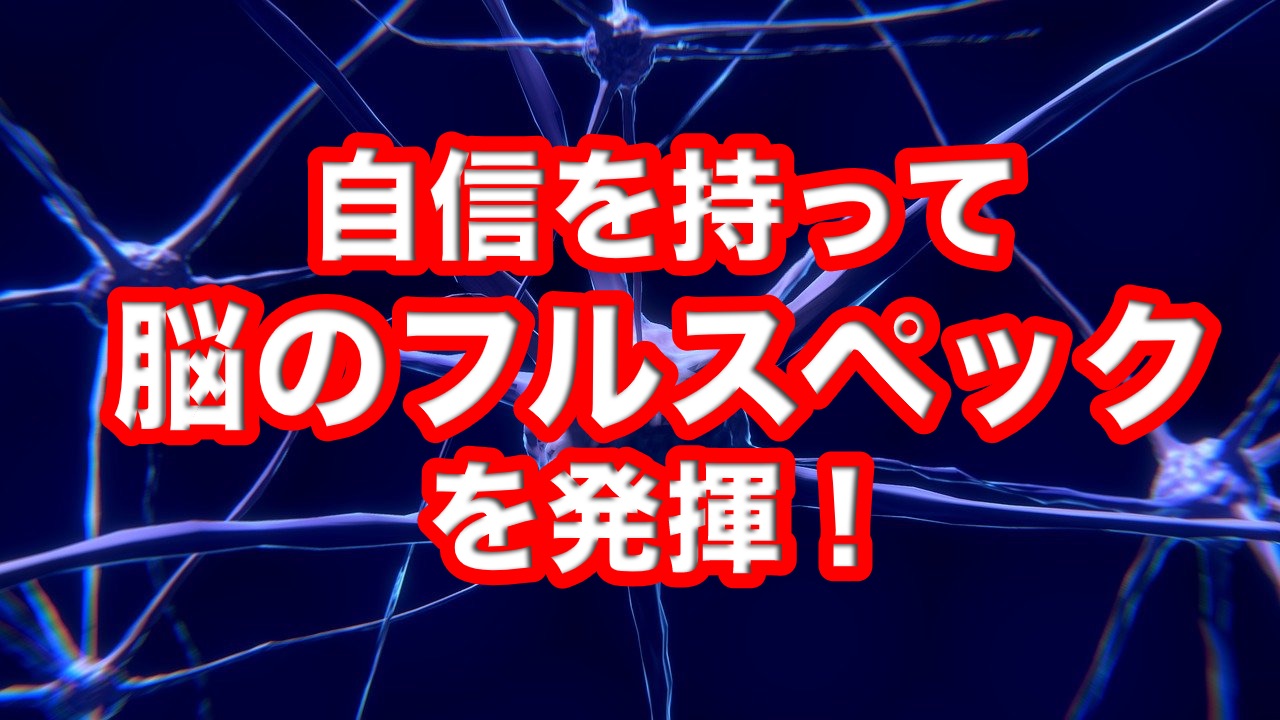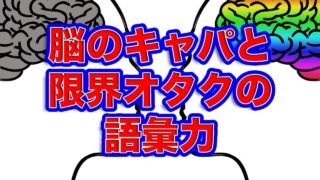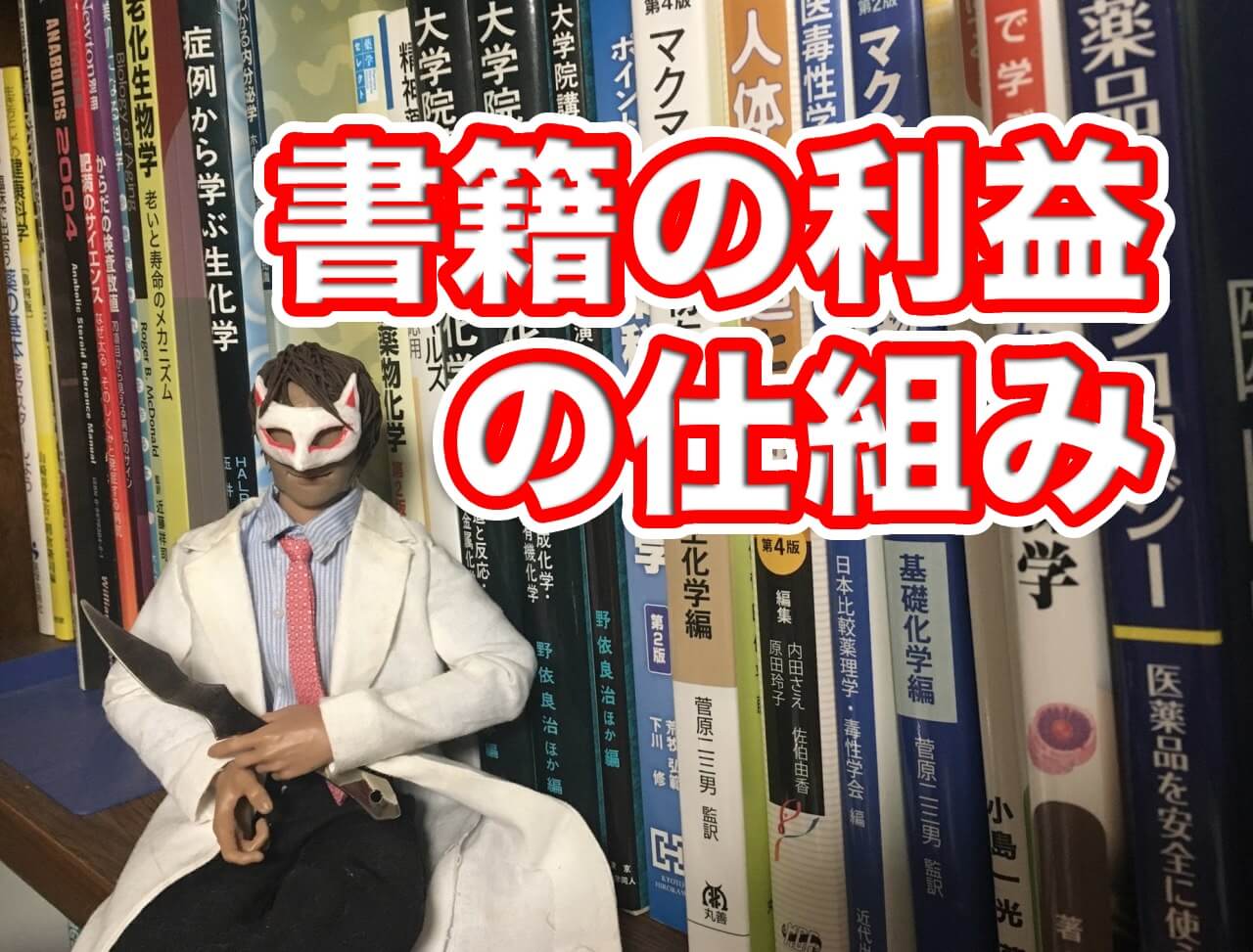初出:2015/11/10 Vol.145 俺日記
改稿:2025/03/14

本日は、脳のリソースの有効活用について触れていこうと思う。

というと、脳をどうやって使うか、という話でしょうか。地頭の良し悪しがありそうですが・・・

いや、向き不向きはあっても、総合的な「脳の性能」にそれほど大きな差はないはずなんだよ。使い方の差は大きくありそうだけどね。

つまり、どうリソースを振り分けるのかで違いが出てくると。

まあゲームじゃあるまいし、そんな簡単にステ振り出来たら苦労しないけども(笑)

何、困ったらパワーで解決すれば良いのだ! 力こそパワー!

POKA先生、ロケランで全てを解決できるのはバイオハザードだけです・・・

だが、「気にしても仕方ないこと」はロケランで吹っ飛ばすつもりで思考から排除してその分のリソースを確保するというのは、考え方として大事かもしれんよ。
脳の総合演算能力は天才も凡才も同じ
脳の演算能力。これに関して自分は、どういう人であっても、総合的な演算量という観点では、そんなに極端な差はないのではないかと思うのです。
天才と呼ばれる人も、凡才で取り柄がないと自己評価している人も。
自分に自信がある人も、自信がない人も。状況判断能力に優れている人も、とっさの判断がままならない人も。
脳が使っているトータルの演算量というのは、ほとんど変わらないはずなのです。
キャパの差は決定的ではない
もちろん、人それぞれ、キャパシティに差はあるでしょう。しかし、それが決定的な差になるとは思いません。
これにはそれなりに根拠もあります。
というのも、昔は「人間は脳の数%しか使っていない」などという言葉が信じられていましたが、実際には、人間の脳は、起きている限りは割とフル稼働している、ということがわかっているからです。
これは、個々人のIQや学歴、人格などで、差はあまり出ません。
脳の活性部位の違い
じゃあなんで頭の良い奴がいて、俺みたいに頭の悪い奴がいるんだよ! と、怒られてしまいそうですね。
うんうん、自分だってもっと頭が良かったらと思うことはある。じゃあ、なんでそういう違いが生まれるか、というと。
「頭の良い人」「頭の鈍い人」の差は、どうやら、脳の活性化している部位の違いから来ているらしい。この差は顕著だそうです。
リソースの振り分けがうまい人
その点も踏まえて、人間の総合演算能力を、仮に100という数値で表すとしましょう。
この100のリソースを、論理的思考や、状況判断、計算力、空気の読み方度合い、そして態度などというパラメータに振り分けており、それこそが「人格」ではないかと思う訳です。
この振り分けや切り替えがうまい人は「頭が良い」ということになるのでしょう。
そして、こうやって考えると、専門分野にパラメータを極振りしていて、そのことに関しては極めて天才的だけど、それ以外は日常生活やら対人関係やらが壊滅的・・・というタイプの人がいるのも納得できるように思います。
脳のリソースを無駄遣いすると処理能力は低下する
この「人格」を形成する中で、自分に自信のない人や、他人にどう思われているかを極端に気にする人には、特に思う事があります。
自信が持てない故に「失敗したらどうしよう」といろんな失敗パターンをシミュレートしては落ち込んだり、他人の反応に気を取られて「こう思われたらどうしよう」と、思いつく限りの最悪の状況を想像したり・・・
演算能力が100あるとして、そのうちの50とか60、下手するとそれ以上を、こうした事に費やしてしまっているのではないかと感じるのです。
細かい事は気にしすぎない方が良い
そうすると必然的に情報処理能力が落ち、結果としてとんちんかんな行動を取ったり、場違いな事をしてしまったりと、失敗に繋がっているのではないでしょうか。
気にしなさすぎも問題を引き起こすことがありますが、人間、言うほど他人のことなど気にしちゃいません。
ズルズルと引っ張って限りある脳のリソースを無駄なシミュレーションに費やすより、スパッと気持ちを切り替えて建設的なことを考えた方が良いと思います。
細かい事は気にしない、というのは、実は結構重要なポイントだと言えるのではないでしょうか。
悪化すると心身の失調に繋がる
人間、失敗から学習して、次はもっと上手くやろう、とするものですが、しかし、こういった状態で引き起こした失敗は、負の想像を強化するばかりで、ロクな事になりません。
この辺が悪化していくと、他人の顔色をうかがうキョロ分だけが上昇していき、最終的には処理能力を超えて思考停止を引き起こしかねません。
これが過剰に続くと、脳の機能失調という形で、レセプタないしリガンドの異常が起こりだし、それが「心の病気」という形で実体を持ってしまうのではないかとも思います。
そうならないためにも、自分というものをよく観る・・・客観視をして、ある程度は「自信」というものを持つべきです。
そもそも人間、何の失敗もせずに生きている訳がありません。多少かっこわるい事があっても胸を張って生きていた方が、人生、楽しいんじゃないかと思います。
追記:どうやら失敗体験の積み重ねは苦手科目を生むらしい
亜留間先生の対談動画で、勉強法について触れています。トライアンドエラーは勉強法としては最低、という話。
曰く、失敗体験の積み重ねは苦手科目を生む、とのこと。
この記事では、「失敗を気にするあまり脳のリソースを無駄遣いしている」「失敗の積み重ねで負の想像を強化し、悪循環に陥る」という、自分の持論に触れたわけですが、どうやらあながち間違いでもなかった模様。
なお、この勉強法の話は亜留間先生の著書「アリエナイ医学事典」に詳細な記事があるので、気になる人はぜひ買って欲しい!
【お悩み相談】人前で堂々と喋るには・・・
お悩み相談で「人前で喋るのが苦手」というものがありました。
結論から言ってこれといった明白な解決策はなく、自分にはその「苦手感」がわからないため、何の役にも立たなかった訳ですが・・・(笑)
一方で、本記事であるように、苦手が先に立ってそれで脳のリソースを消費してしまうと、よりドツボな状況になっていってしまうので「自信を持つ」というのも一つの対策となるような・・・気がします(笑)
著者紹介

作家、科学監修。「科学は楽しい!」を広めるため科学書分野で20年以上活動。著作「アリエナイ理科」シリーズ累計50万部突破。原作を務めるコミックス「科学はすべてを解決する!!」も50万部を超える。著作「アリエナクナイ科学ノ教科書」が第49回・星雲賞ノンフィクション部門を受賞。週刊少年ジャンプ連載「Dr.STONE」においては漫画/アニメ共に科学監修を担当。TV番組「世界一受けたい授業」「笑神様は突然に・・・」NHK「沼にハマってきいてみた」等に出演。ゲーム実況者集団「主役は我々だ!」と100万再生を超えるYouTube科学動画を多数共同製作。独自YouTubeチャンネル「科学はすべてを解決する!」チャンネル約30万登録やTwitterフォロワー16万人以上。教育系クリエイターとして注目されている。関連情報は https://twitter.com/reraku
「アリエナイ毒性学事典」好評発売中です!
「アリエナクナイ科学ノ教科書2」好評発売中です!
新刊「マンガでわかる! 今日からドヤれる科学リテラシー講座 教えて!夜子先生」好評発売中です!
関連記事
ヘルドクターくられの「脳のキャパ論」
自信を持つ事で新しい環境に適応する
コミュ障は訓練して直そう
鬱とアルコールと季節による失調
ヘルドクターくられの「俺コラム」記事一覧

「パーソナリティ障害」記事一覧

宣伝
ニコニコ動画にて有料チャンネル「科学はすべてを解決する!! ニコニコ秘密基地」を開設しました!

「アリエナイ理科式世界征服マニュアル」が改訂版となって新発売されます!
「アリエナイ医学事典2」好評発売中です!
「アリエナイ医学事典 改訂版」好評発売中です!
「アリエナイ理科ノ大事典3」、好評発売中です!
くられ先生の単著「アリエナイ毒性学事典」好評発売中です!
工作系に特化した「アリエナイ工作事典」好評発売中です!
「アリエナイ理科ノ大事典」改訂版が発売中です!
「アリエナイ理科ノ大事典2」、好評発売中です。