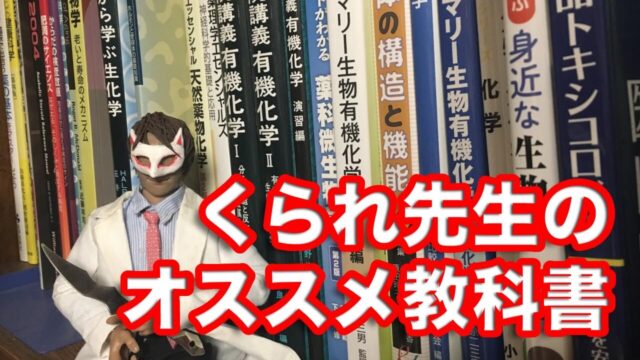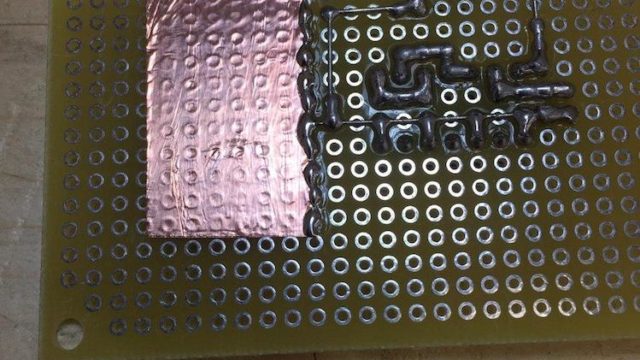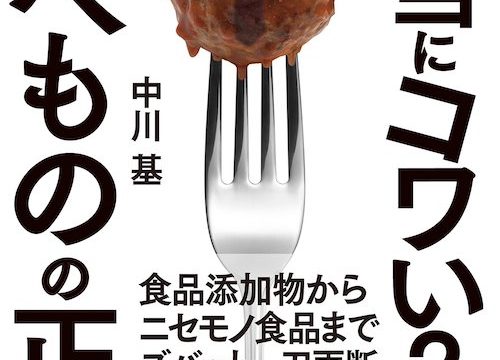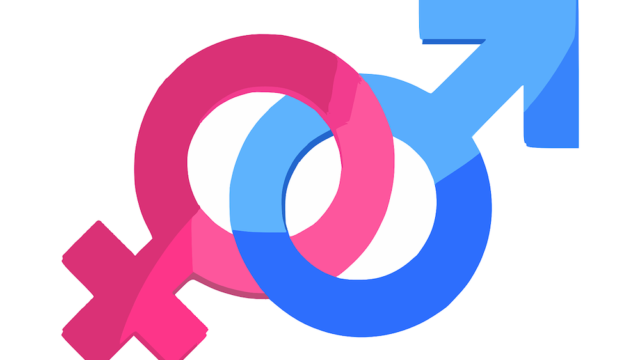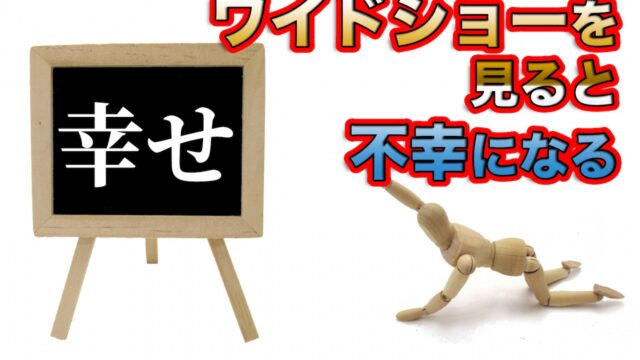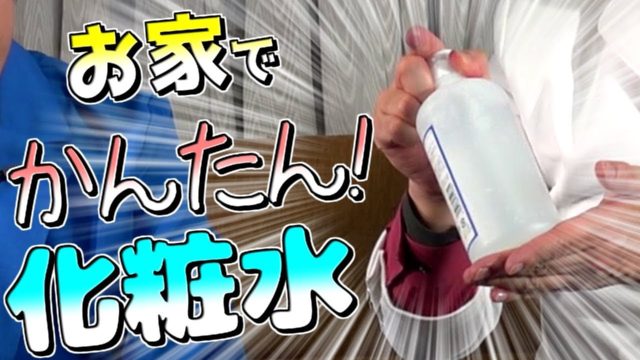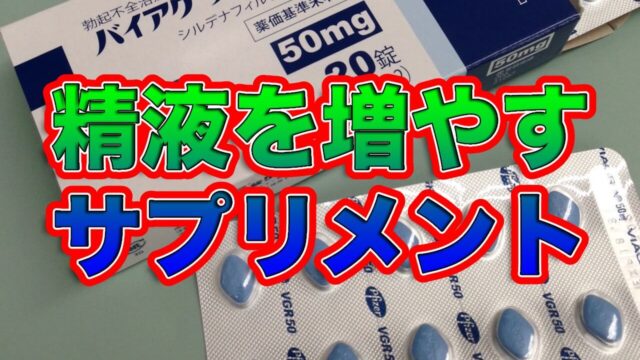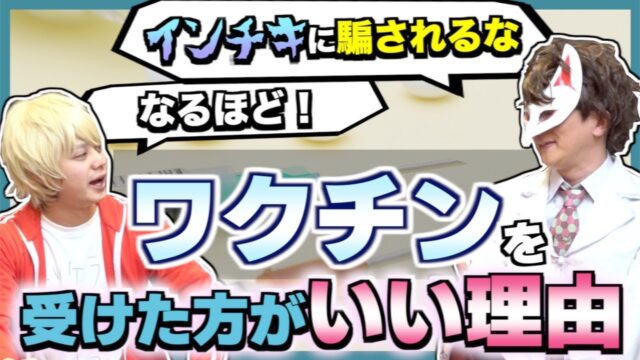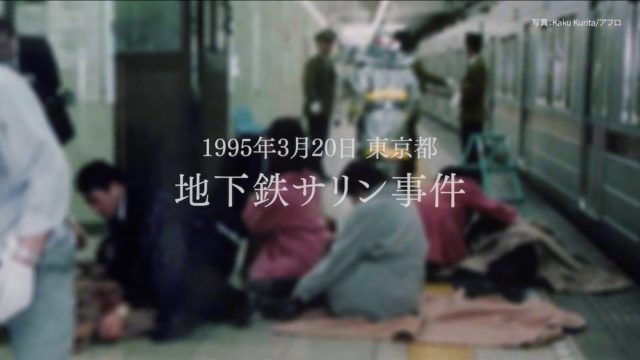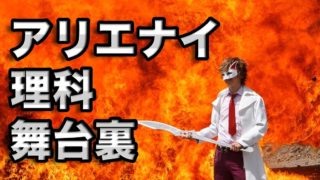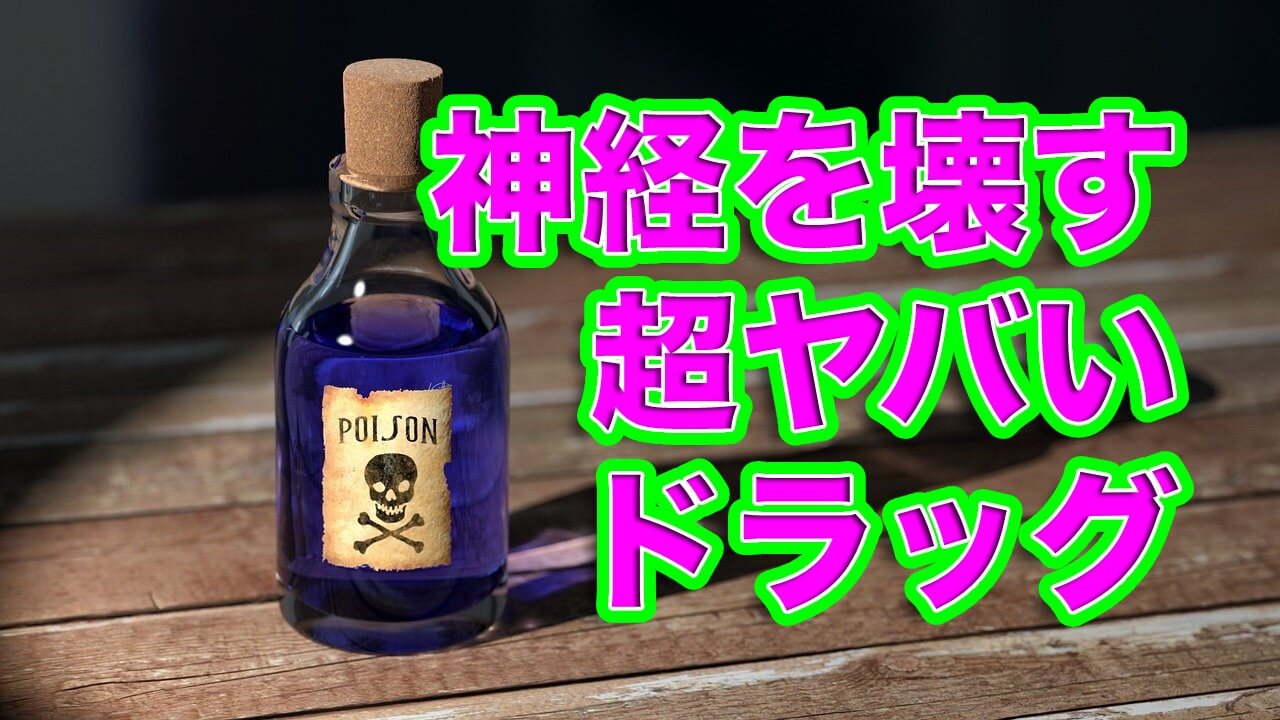初出:2017/08/08 Vol.236 花火の科学
改稿:2023/08/18

今日は花火の科学ですか、先生。炎色反応ですよね。

うむ。その通りなのだが、花火のあの絶妙な色合いを出すのは職人芸なんだよね。

より美しくするために長い時間をかけて研鑽してきた結果という事ですね。素晴らしい。

花火と聞いたので、特大の発射台を用意したぞ!

何この漫画みたいな発射台・・・人間が入れそうなんだけど、何、この火薬玉を詰めればいいの?

うむ。その通りなのだが、それはオマケでな(ゲシッ)

ちょっ、今頭からいきましたよ? 何かヤバい音がしましたけど・・・あ、足がバタバタしてる。

はっはっは、活きのいい弾体だな!「お前の炎色反応が何色か見てやろう!」というのがこの装置だ! 発射ァ!

・・・・・・BRSKファーーーーー!
花火と理系あるある・・・あるよね?
夏と言えば花火です。
花火を見ると「あーリチウム、これは銅かな?」などと、炎色反応ネタで雑なウンチクを話すうっとうしい奴がいるものです(笑)。
何? そんな奴はいない? いや、理系あるあるではないか!
ここは是非とも、さらなる知識を得てウンチクを増強し、周囲をもっとドン引きさせて欲しいものである。
という訳で、今回は花火について科学的に解説していきましょう。
・・・本当に周囲をドン引きさせてモテなくなっても責任は取れないのであしからず。
花火と法律
まず、花火は当然火薬を扱う物ですから「火薬類取締法」などの法律で厳密に管理されています。
夏祭りの主役たる打ち上げ花火などは、「煙火打揚従事者」でなければならず、花火の製造はまた別に免許が必要です。
スーパーやホームセンターなどで買える「玩具用煙火」も吹き出し花火からクラッカーボール、笛ロケット、流星ロケット、へび花火に至るまで、それぞれの分類に応じた火薬の使用限界量までが決められています。
日本という国が狭いため、その制限量は諸外国よりは少なめです。
法的な縛りで海外ほど見栄えが良くない
海外の手持ち花火などはネットの動画サイトなどで見ることができますが、例えばアメリカの花火などは手持ち花火でも日本製が残念になるくらいに大火力で見栄えがするものが売られていたりします。
日本では総薬量規制があるために派手な花火が販売できず、YouTubeなんかで派手な花火をみてうらやましがるしかないわけです。
また大半市販されるのは大半が中国からの輸入の極めて安いものばかりで、国産の手持ち花火は大半が赤字になるため大半が廃れていく一方です。現在では数社が細々と作っているに過ぎないのが現状。
先日も「かんしゃく玉」の製造終了のニュースが話題になっていました。国産業が衰退していくのは残念なものです。
炎色反応の話
さて、肝心の花火の色である炎色反応とはなんでしょうか?
元素はエネルギーが高まると、余分なエネルギーを独特の波長の電磁波として放出します。これがスペクトルというもので、温度によって元素によって独特です。
宇宙望遠鏡などで、人類が行ったことも無い星の構成成分が分かるのも、こうした光を分析し解析しています。
花火の美しい色も、この炎色反応によるものであると説明するのは理系人が理系人に見え、風情が無いと揶揄される象徴的なお話で打ち上がるたびに元素名をいちいち言うのは考え物です。
花火の職人芸
さて、「炎色反応」というもの。中高学校の化学では、金属を見分けるのに使う方法として紹介されていますが、実際は金属以外のあらゆる物質にスペクトル、つまり炎色反応が存在します。
ただし、人間の知覚できる電磁波(可視光)は非常に幅が狭いので、コンピュータ解析上での色と我々が感じる色は別物です。そして我々が分かりやすく見える色と元素の組み合わせが炎色反応として知られているというわけです。
そして温度によって色は変わるので、紫などの絶妙な色合いはまさに組み合わせの職人芸なのです(カリウムじゃないよw)。
ちなみに赤〜ピンクに使われているのが炭酸ストロンチウム、緑色は硝酸バリウム、黄色は炭酸カルシウム、青は酸化銅と重曹、キラキラと白色に光るのは金属アルミニウム粉、金色はチタン系の何か・・・だそうです。
炎色反応をガチで実験する動画
レイユール先生の動画「ガチ実験」シリーズで炎色反応について触れました。
動画の途中で触れられている、温度の違いによる色の変化は、この記事で触れた花火の色合いの妙に繋がる部分ですね。興味がある方はぜひ動画もご覧ください。
基礎的な実験に見えて、意外と炎色反応は奥が深いのです。
著者紹介

作家、科学監修。「科学は楽しい!」を広めるため科学書分野で20年以上活動。著作「アリエナイ理科」シリーズ累計50万部突破。原作を務めるコミックス「科学はすべてを解決する!!」も50万部を超える。著作「アリエナクナイ科学ノ教科書」が第49回・星雲賞ノンフィクション部門を受賞。週刊少年ジャンプ連載「Dr.STONE」においては漫画/アニメ共に科学監修を担当。TV番組「世界一受けたい授業」「笑神様は突然に・・・」NHK「沼にハマってきいてみた」等に出演。ゲーム実況者集団「主役は我々だ!」と100万再生を超えるYouTube科学動画を多数共同製作。独自YouTubeチャンネル「科学はすべてを解決する!」チャンネル約30万登録やTwitterフォロワー16万人以上。教育系クリエイターとして注目されている。関連情報は https://twitter.com/reraku
「アリエナイ毒性学事典」好評発売中です!
「アリエナクナイ科学ノ教科書2」好評発売中です!
新刊「マンガでわかる! 今日からドヤれる科学リテラシー講座 教えて!夜子先生」好評発売中です!
関連記事
黒色火薬の話
火遊びの舞台裏:たかが花火を思わず遊ぶ時は防火対策をしっかりしましょう
火起こしは意外と大変
オイルマッチのパワーアップ
ご家庭で超火力「ターボ花子」
宣伝
ニコニコ動画にて有料チャンネル「科学はすべてを解決する!! ニコニコ秘密基地」を開設しました!



「アリエナイ理科式世界征服マニュアル」が改訂版となって新発売されます!
「アリエナイ医学事典2」好評発売中です!
「アリエナイ医学事典 改訂版」好評発売中です!
「アリエナイ理科ノ大事典3」、好評発売中です!
くられ先生の単著「アリエナイ毒性学事典」好評発売中です!
工作系に特化した「アリエナイ工作事典」好評発売中です!
「アリエナイ理科ノ大事典」改訂版が発売中です!
「アリエナイ理科ノ大事典2」、好評発売中です。