初出:2018/02/13 Vol.263 チョコレートの科学
改稿:2024/02/11

おや先生、やけに甘ったるい匂いがすると思ったら、チョコですか?

シーズン的にチョコの作り方を聞かれる事もあるんで、温度管理が雑でも大丈夫な方法でもと思ってね。試作品食べる?

あ、いただきます・・・ぐはっ!

あれ、おかしいな、今回はマジで変な物は入れてないんだが・・・罰ゲーム用はこっちだし。

せ、先生、私、アーモンドやクルミには、アレルギーが・・・(がくり)

あー・・・抗ヒスタミン薬はどこだったかな・・・
※中の人は本当にアレルギー持ちです。
意外と難しい手作りチョコ
2月を迎えると、バレンタインのシーズンが到来します。
「今年はチョコを手作りしよう!」という人もいるでしょう。
しかし、チョコレートというものは、非常に温度管理の難しい食べ物です。
レシピサイトを見ながら、チョコを溶かして型に入れて固めて・・・という工程で手作りチョコを作ると、残念ながらだいたいマズいものが出来上がってしまいます。
材料のチョコは美味しかったのに、固めるだけでマズくなる。どうしてでしょう?
今回はこの辺の解説と、そして手作りチョコを美味しくする科学的な裏技について触れていきます。
手作りチョコの失敗要因は「テンパリング」
溶かして再度固めただけなのに、チョコがマズくなる。
この現象は、チョコレートに含まれるカカオバターの結晶構造によります。
カカオバターはパルミチン酸、ステアリン酸、オレイン酸という脂肪酸で大半構成されていて、パルミチン酸やステアリン酸は本来ろうそくくらいの融点で非常に固い脂肪酸です。
一方オレイン酸は常温では液体の脂肪酸で融点は16℃。
この異常な高低差のある脂肪酸のバランスから、テンパリングという工程が必要になり、それに失敗するとボソボソの結晶構造になりやすい・・・つまり、マズくなるわけです。
テンパリングは職人芸の世界
テンパリングとは一端50℃くらいに融かしたチョコレートを型に入れ、ここで急冷せず、25〜27℃に冷やし、再び31~32℃に加熱して少し柔らかくしてから、再度冷やし固めるという面倒な行程のことです。
このテンパリングの温度に関しては、メーカー別に決まっています。
単に「溶かして固め直すだけじゃん」とは行かないのは、このクッソ面倒なテンパリングが必要だからです。
日本の100円チョコのレベルの高さ
この辺、丁寧に丁寧に温度管理をしていけば、手作りチョコも口当たりよく、美味しく作れます。
が、しかし、やはりそれは難しく大変な職人仕事の世界なのです。
日本では当たり前に100円やそこらで美味しい板チョコが手に入りますが、使ってる原材料から技術に至るまで、かなり高度な事をやっています。
海外のそこそこ高いチョコが案外美味しくなかったとか、そういう現象が起きるほどです。
そんな訳で難しいのですが、そこで終わってしまうと今回の記事が成立しないので(笑)、もう少しお手軽な、科学的な裏技を紹介しましょう。
手作りチョコの科学的裏技
科学的裏技、といってもそう大層なことではありません。
手作りチョコを作る際は、バターやココナッツオイルといった、融点のほどほどの油脂を混ぜれば良いのです。
これらを適量、混ぜ込んでから固めれば、多少、温度管理が雑でも、ボソボソになりにくい、つまりは失敗しにくくなります。
なお、今回は食用としてココナッツオイルをオススメしている訳ですが、冬場の手荒れ防止なんかにも良い感じです。この辺は記事があるので関連記事をご参考にどうぞ。
余談:手作り用の「クーベルチュール」は最高に美味しい
ちなみに市販されている溶かして使うバレンタインチョコは、そんな温度管理をしなくても、そこそこの品質に調整されたチョコレート・・・のようなものです。
厳密には準チョコレートといって、チョコレートにアレコレ既に足したものです。なので、公正取引委員会の認定的に言うとバレンタイン準チョコレートと呼ぶのが正しいのです。
ちなみにお菓子用のチョコだと、不二製油のクーベルチュールが最高に美味しいです。
特にホットチョコにすると美味しい。個人的には、ビター寄りの方が好みなので、ミルクにビターチョコを少し混ぜたりします。
同じく、このmamapanのロングランアーモンドミルクもマジで美味しい。
というわけで、バレンタインの手作りチョコに失敗しない裏技の話でした。ハッピーバレンタイン!
自宅でできるスタバ的チョコドリンク
本記事で紹介したように、製菓用のチョコというものがあり、それを活用すると美味しいココアからスタバに出てくるようなフラペチーノ的なチョコドリンクを作る事もできます。
動画で紹介しているので気になる人はぜひ。粉のココアをただ作るより断然美味しくなります。
なお動画中のミキサーはかなり強力なものですが、氷を砕くのに対応しているものなら大丈夫だと思います。
著者紹介

作家、科学監修。「科学は楽しい!」を広めるため科学書分野で20年以上活動。著作「アリエナイ理科」シリーズ累計50万部突破。原作を務めるコミックス「科学はすべてを解決する!!」も50万部を超える。著作「アリエナクナイ科学ノ教科書」が第49回・星雲賞ノンフィクション部門を受賞。週刊少年ジャンプ連載「Dr.STONE」においては漫画/アニメ共に科学監修を担当。TV番組「世界一受けたい授業」「笑神様は突然に・・・」NHK「沼にハマってきいてみた」等に出演。ゲーム実況者集団「主役は我々だ!」と100万再生を超えるYouTube科学動画を多数共同製作。独自YouTubeチャンネル「科学はすべてを解決する!」チャンネル約30万登録やTwitterフォロワー16万人以上。教育系クリエイターとして注目されている。関連情報は https://twitter.com/reraku
「アリエナイ毒性学事典」好評発売中です!
「アリエナクナイ科学ノ教科書2」好評発売中です!
新刊「マンガでわかる! 今日からドヤれる科学リテラシー講座 教えて!夜子先生」好評発売中です!
関連記事・動画
チョコレートを使った面白実験
手荒れ防止にココナッツオイル
チョコミルクを入れても美味しいカップアイス再現
コアントローというリキュール・チョコとの相性抜群でちょっと大人な感じに。
チョコレートリキュールの牛乳割りも美味しい
「レディーキラー」カクテルにも、カカオリキュールが使われているものがちらほら
宣伝
ニコニコ動画にて有料チャンネル「科学はすべてを解決する!! ニコニコ秘密基地」を開設しました!

「アリエナイ理科式世界征服マニュアル」が改訂版となって新発売されます!
「アリエナイ医学事典2」好評発売中です!
「アリエナイ医学事典 改訂版」好評発売中です!
「アリエナイ理科ノ大事典3」、好評発売中です!
くられ先生の単著「アリエナイ毒性学事典」好評発売中です!
工作系に特化した「アリエナイ工作事典」好評発売中です!
「アリエナイ理科ノ大事典」改訂版が発売中です!
「アリエナイ理科ノ大事典2」、好評発売中です。



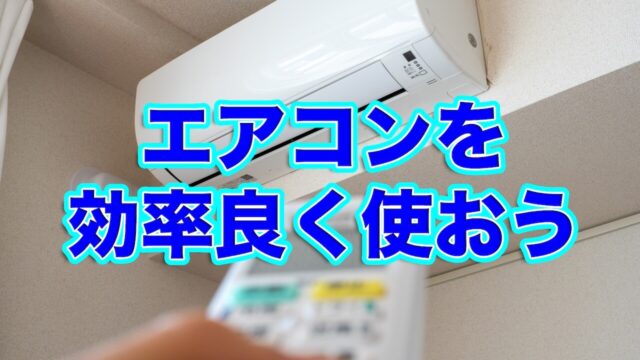


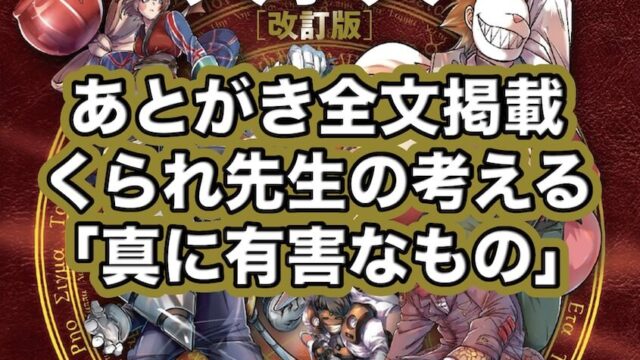

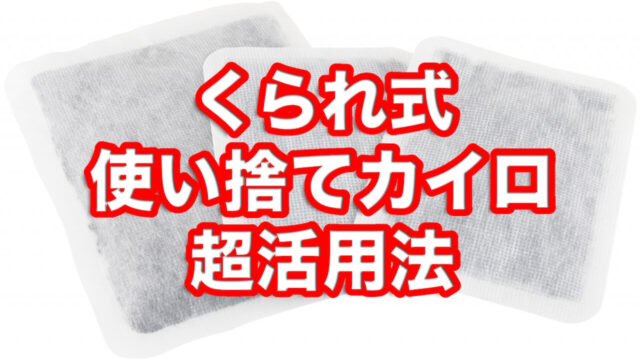


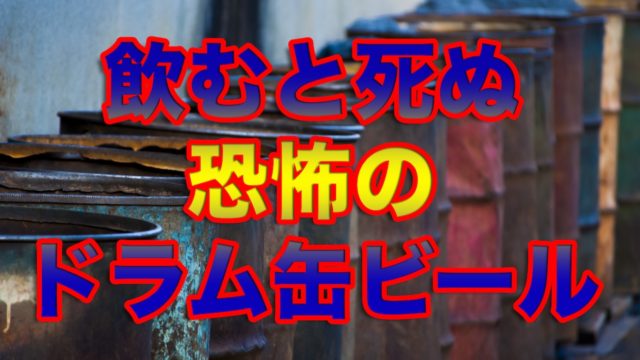



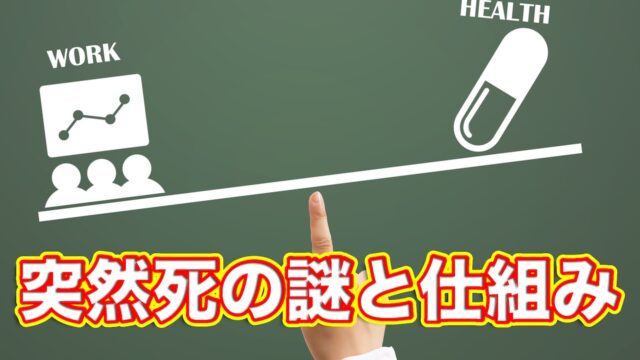



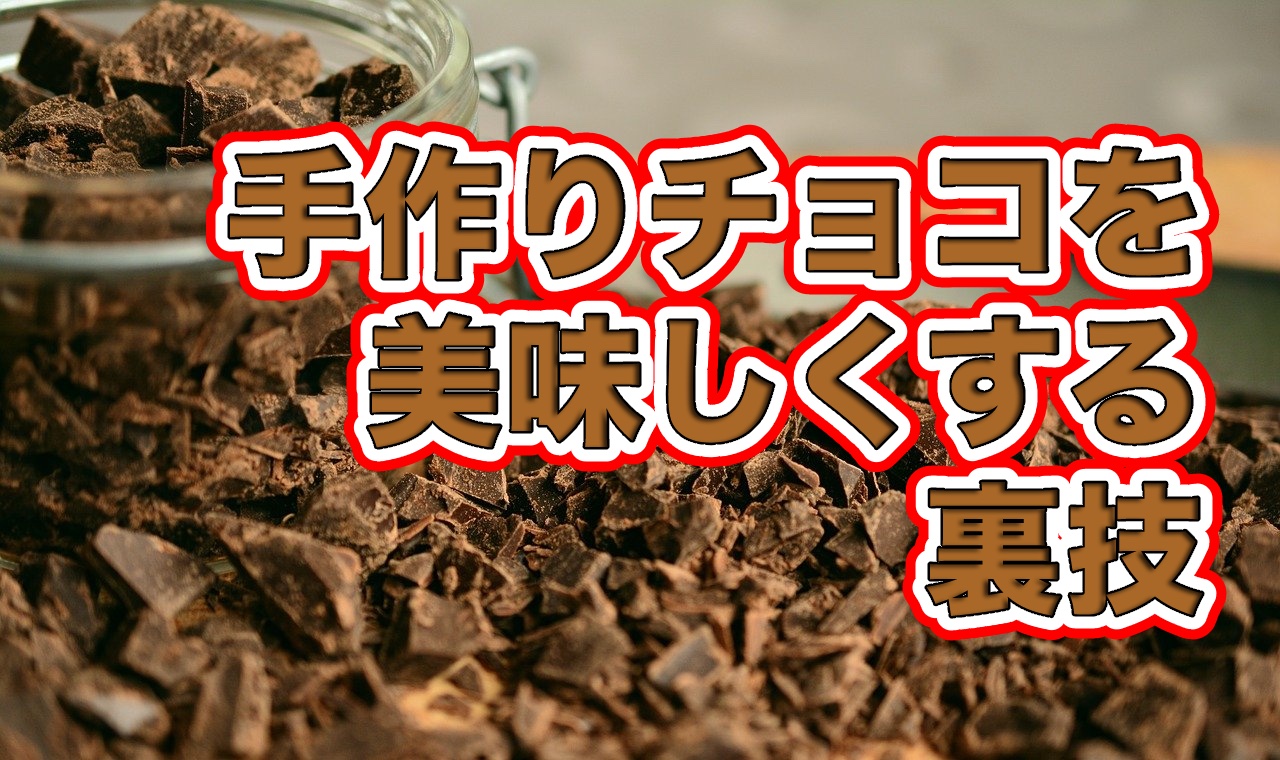













































![[冷凍]ハーゲンダッツ ミニカップ クリスプチップチョコレート 110ml](https://m.media-amazon.com/images/I/51JHV+0a1OL._SL160_.jpg)




































































